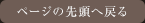ここから本文です。
更新日:2020年12月18日
特別史跡多賀城跡附寺跡第3次保存管理計画
保存管理計画とは
史跡等を適切に保存し、次世代へと確実に伝達していくため、史跡等の本質的価値と構成要素を明確化し、それらを適切に保存・管理していくための基本方針、方法、現状変更等の取扱基準の策定等を目的としています。
特別史跡指定及び保存の経緯
多賀城跡附寺跡は、全国的にも早く奈良の平城宮跡などと共に大正11年に史跡に指定され、保存事業は、昭和35年からの廃寺跡、続く38年からの多賀城政庁跡の発掘調査の成果により、昭和41年に特別史跡に昇格しました。その後、多賀城に関連する遺跡が相次いで発見され、これまで数回の追加指定が行われています。
保存事業は、多賀城市(管理団体)が土地公有化事業と維持管理事業を、宮城県が発掘調査事業と環境整備事業を担当し、相互協力のもと実施してきました。
特別史跡多賀城跡附寺跡保存管理計画の目的
わが国古代における東北地方統治の原点であり、平城宮跡・大宰府跡と共に三大史跡と称されている多賀城跡及び廃寺跡等を適切に保存管理し、整備活用するための施策を明らかにすることを目的として策定しました。
また、第2次保存管理計画策定から20年あまりが経過し、特別史跡の追加指定や周辺社会環境の変化、調査研究の進展により、計画内容と現状がそぐわないものとなり、計画見直しの必要性が生じてきていました。
第3次保存管理計画における主な改正点
特別史跡の構成要素の再設定
新たに「生活文化構成要素」を設定し、保存管理計画の対象をより明確にしました。
- 遺跡構成要素~多賀城に直接関連する歴史的構成要素で、時代を超えて保護・継承すべき不変的なもの。
[多賀城に係る遺構・遺物/立地環境(低丘陵地形)/自然環境(湿地域)他] - 生活文化構成要素~主に多賀城廃絶後に形成された社会的構成要素で、時代とともに推移していく可変的なもの。
[宅地/農地・林地/宗教施設/公共公益施設/一般文化財・保存樹 他]
地区区分の変更
上記視点に基づき、遺跡構成要素の適切な保存管理を目的に、積極的に公有化と整備活用を図る「S重点遺構保存活用地区」を新たに設置するなど、地区区分を見直しました。
その他の改正点
- 既存住宅において、建築面積の120%以内の新築・増改築の許可(ただし、意匠・構造等は特別史跡の景観形成にふさわしいもの)
- 環境整備における市の参画
- 積極的な史跡の活用(地域住民を講師とした歴史的食文化体験学習、里山体験学習など)
計画書
特別史跡多賀城跡附寺跡第3次保存管理計画書
- 表紙・目次・第1章(PDF:2,205KB)(12ページ)
- 第2章(PDF:9,290KB)(14ページ)
- 第3章(PDF:5,648KB)(26ページ)
- 第4章(PDF:7,854KB)(18ページ)
- 第5章(PDF:5,013KB)(25ページ)
- 第6章(PDF:1,780KB)・附章(21ページ)
概要版
- 第1章(PDF:5,984KB)(9ページ)
- 第2章(PDF:8,490KB)(33ページ)
- 第3章(PDF:1,015KB)(12ページ)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください