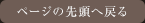ここから本文です。
更新日:2025年7月23日
埋蔵文化財調査センター常設展
埋蔵文化財調査センター展示室では、常設展「古代都市多賀城」を開催しています。
古代、多賀城の南面にまち並みが広がっていた山王遺跡、市川橋遺跡からの出土資料を中心に展示し、6つのコーナーを設けて紹介しています。

ようこそ!多賀城市埋蔵文化財調査センター展示室へ。

入口を入ると、令和6年に国宝に指定された多賀城碑のレプリカが迎えてくれます。
1.多賀城のはじまり
大化の改新以降、天皇や貴族を中心とした律令に基づく国づくりが始まり、その支配は東北地方にまでおよびました。多賀城は律令国家の版図拡大に応じて神亀元年(724)に設置された城柵で、東北地方の中心として重要な役割を担いました。

多賀城の成り立ちを説明したパネル。「古代都市多賀城」の世界へと誘います。
2.まち並みの形成と土地利用
宝亀11年(780)の伊治公呰麻呂(これはりのきみあざまろ)による襲撃事件後、炎上した多賀城の復興が進み、この時期に多賀城南面における都市建設も始まりました。
直線道路によって整然と区画されたまち並みは9世紀中頃から後半期に最大となり、多賀城を支える諸機能と人々の生活の場が一帯となった空間は、都市と呼ぶにふさわしい姿でした。
ここでは、「古代都市の発見」、「多賀城とまち並みの変遷」、「都とつながるまち並みの基準線」、「水路を組み込んだ都市計画」、「まち並みに住まう人々」、「都市の生産域」の構成でまち並みの概要を紹介しています。

多賀城市内西部に眠る古代のまち並み。直線道路によって整然と区画されていました。
3.国守館
国守(くにのかみ)とは都から地方に派遣される国司の長官のことです。陸奥国の長官=陸奥守(むつのかみ)の住まいは、東西大路に面した区画で発見されました。
建物は10世紀前葉のもので、多賀城政庁の維持・管理が徹底されなくなっていたこの時期、政務と日常の住まいを兼ねた空間であったと考えられます。
ここでは、「国守館の発見」、「国守にふさわしい格式高い館」の構成で、全国で初めて発見された国守館について紹介しています。

大木をくり抜いて作られた井戸側(写真右側)。

「右大臣殿餞馬収文」と記された題箋軸木簡。国守館と結論付けられる手がかりのひとつになりました。
4.まち並みに集まる人・モノ
多賀城は水陸交通の要衝に築かれ、様々な人やモノが行き交う交流の場として発展しました。
陸奥国内や北方世界から多賀城へ、多賀城から都へ、都から多賀城へ、活発な人・モノの動きの痕跡は、まち並みの出土資料からも垣間見ることができます。
ここでは、「古代国家と道路」、「陸奥国内の地名」、「陸奥国内から多賀城への人・モノの動き」、「都から多賀城へ赴任した人」、「都人のあこがれ陸奥国からの貢納品」の構成で、多賀城やまち並みの交通や物流、人の流れを紹介しています。

国産の灰釉・緑釉陶器、中国産の青磁・白磁が多数出土しています。

馬具の一種である、壺鐙(つぼあぶみ)。鉄製の鐙に黒色漆が塗られていました。
5.人々の信仰と祭祀
まち並みの中では、穢れを祓ったり、神を鎮めたり、仏に祈ったりと都と同じような祭祀やまじないが行われていました。これらの祭祀で用いた様々な祭祀具がまち並みから多数見つかっています。
ここでは、「祭祀の場と様々なまじないの道具」、「万灯会と多賀城廃寺」、「観音寺の文字が示す多賀城廃寺の名称」の構成で、まち並みの人々の信仰について紹介しています。

人面墨書土器や人形、斎串など水辺で行われた穢れを祓う祭祀で使われた祭祀具の数々。

仏教行事・万灯会で使用された土器のひとつ。「観音寺」と記されており、多賀城廃寺の名称と考えられています。
6.まち並みの終焉
10世紀に入ると古代的な律令体制が衰退し、多賀城も11世紀半ばに廃絶したと考えられています。それに伴って、多賀城南面のまち並みも終焉を迎えます。

多賀城はその役割を終えて、時代は新たな社会へと移りゆきます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください