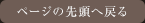ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
平成24年度の発掘調査情報
平成24年度には、市内で45件の発掘調査を実施しました。これらは、東日本大震災からの復興と生活再建を目的とした個人住宅や共同住宅建築、宅地造成工事などに伴う調査です。
ここでは、地域の歴史を解明するうえで、重要な遺構が発見された10件の調査を取り上げて、ご紹介します。
新田遺跡の調査(第86次調査)

- 調査場所多賀城市新田字後地内
- 調査期間4月6日から4月21日
- 調査面積50平方メートル
調査成果
古墳時代中期(西暦400年代頃)の大規模な溝跡と、古墳時代後期(西暦500年から600年頃)の竪穴住居跡を発見しました。
山王遺跡の調査
町地区東部の調査(第117・118次調査)


- 調査場所多賀城市南宮字町地内
- 調査期間第117次:10月18日から12月12日第118次:10月19日から11月27日
- 調査面積第117次:61平方メートル第118次:43平方メートル
調査成果
- 第118次調査では、古代(奈良・平安時代)のまち並みを碁盤の目のように区画する道路網のうち、北1東西道路跡を発見しました。この道路跡は両側に側溝をもち、2回の改修が行われていることがわかりました。
- 第117次調査区は、第118次調査区の北隣に位置し、ここから敷地の北辺と東辺を区画する古代の材木塀跡を発見しました。
- 道路跡と材木塀跡に区画された敷地内で、5棟の掘立柱建物跡を発見しました。これらは、位置を変えながら何度か建て替えられていることがわかりました。
町地区西部の調査(第103・106次調査)


- 調査場所多賀城市南宮字町地内
- 調査期間第103次:5月23日から6月14日第106次:5月26日から6月12日
- 調査面積第103次:80平方メートル第106次:65平方メートル
調査成果
- 2つの調査区で、江戸時代の掘立柱建物跡、井戸跡、堀跡などを発見し、いずれも屋敷地として利用されていたことがわかりました。また、当時の日常生活の様子がしのばれる、陶磁器や土人形なども見つかりました。
- 発見された屋敷跡は、江戸時代の塩竈街道沿いのまち並みを形成していたものと考えられます。
中山王地区の調査(第108・120次調査)


- 調査場所多賀城市山王字中山王地内
- 調査期間第108次:7月11日から7月25日第120次:11月15日から1月12日
- 調査面積第108次:63平方メートル第120次:42平方メートル
調査成果
- 古代(奈良・平安時代)の掘立柱建物跡や溝跡などを発見し、ここが碁盤の目のように区画されたまち並みの一角であったことがわかりました。
- 中世(おもに鎌倉・室町時代)の掘立柱建物跡や井戸跡、江戸時代の掘立柱建物跡などを発見し、このあたりが長期にわたり人々の生活の場となっていたことがわかりました。
市川橋遺跡の調査(第85・86次調査)


- 調査場所多賀城市城南2丁目・城南1丁目地内
- 調査期間第85次:4月25日から5月26日第86次:5月30日から7月2日
- 調査面積第85次:96平方メートル第86次:90平方メートル
調査成果
- 第85次調査では、北西から南東に斜めに延びる、古代(奈良・平安時代)以前の大規模な河川跡を発見しました。この河川は、調査区の西側で南に延びる直線的な流路に改修され、多賀城に物資を運ぶための運河として利用されました。改修後、本調査区の場所では埋め立てられたと考えられ、埋土の中から当時の土器が多量に出土しました。
- 第86次調査では、古代の掘立柱建物跡などを発見しました。調査区付近は、碁盤の目のように区画されたまち並みのメインストリートである南北大路に近く、多賀城の城外でも重要な地区と考えられています。
桜井館跡の調査(第2次調査)


- 調査場所多賀城市中央1丁目地内
- 調査期間11月2日から1月31日
- 調査面積440平方メートル
調査成果
- 多賀城市役所西側の小高い丘陵上に位置します。今回、確認調査を実施した結果、中世(おもに鎌倉・室町時代)の館跡に伴う土塁や空堀を発見しました。
- 本館跡については、平成25年度に本発掘調査を実施します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください