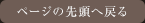ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
縄文時代
縄文時代は、旧石器時代までの寒冷期が終わり、温暖化が進んだおよそ15,000年前から始まる時代です。気温が上昇したことにより、針葉樹から落葉樹へと植生が変化し、クリやクルミなどの木の実が豊富に実りました。これら豊富な食料を調理するための土器や、林の中を駆け回るシカやイノシシを狩るための弓矢など、新たな道具も登場します。一方海岸部では、貝の採集や漁撈(ぎょろう)なども行われるようになり、鹿角などを加工した釣り針や銛(もり)なども作られるようになりました。こうした豊かな自然と、それを利用しようとする縄文人の知恵や工夫により、旧石器時代までの遊動的な生活から、竪穴住居(たてあなじゅうきょ)に住み大規模な集落を構える定住的な生活へと変化します。

縄文人の生活(縄文カレンダー)
多賀城跡内の縄文時代遺跡
縄文時代前期は、約6,000年前をピークとする「縄文海進(じょうもんかいしん)」の時代と言われており、現在よりも海面が2メートルから3メートル高く、海岸線が内陸まで及んでいた時代でした。本市北部の松島丘陵上にある多賀城跡内では、現在の海岸から内陸に入り込んだ場所であるにも関わらず、この頃の貝塚(縄文人がごみを捨てた跡)が発見されています。
金堀(かなほり)貝塚と命名されたこの貝塚には、幅7m、厚さ60cmの範囲にわたってハマグリを主体とした貝層が広がっていました。この貝層は、昭和62年に史跡見学に来た小学生が貝殻と土器を拾って旧東北歴史資料館に鑑定を依頼したことが発見のきっかけと言われています。貝層発見に先立って昭和48年に行われた発掘調査では、土器片のほか、石斧(せきふ)、石匙(いしさじ)、搔器(そうき)などの作業道具のほか、矢じりや尖頭器(せんとうき)などの狩猟具も発見されており、生活の拠点となっていたことが伺えます。この遺跡は、その後約5,000年前の縄文時代中期中葉の土器も発見されており、断続的に人々が居住していたことが分かっています。そのほか、多賀城城内南西部の五万崎遺跡においても、おおよそ同時期の土器が発見されています。

金堀貝塚の風景
大代地区の縄文時代遺跡
約3,400年前の縄文時代の終わり頃になると、「亀ヶ岡式土器(かめがおかしきどき)」と言われるような精巧で優美な土器や、遮光器土偶(しゃこうきどぐう)などが作られるようになります。市内においても、大代地区でこの時期の遺跡が発見されています。
なかでも、大代貝塚(橋本囲(はしもとがこい)貝塚)は、今からおよそ100年前の大正8年に調査が行われており、これは市内でも最も古い発掘調査です。この調査では、ハマグリやカキを主体とする貝塚の中から、4体分の縄文人骨が発見されています。この発見は、いち早く全国的な学会で紹介され、日本考古学研究の黎明期に大きく貢献しました。
本市周辺の松島湾沿岸は、全国屈指の貝塚密集地帯であり、東松島市里浜(さとはま)貝塚、七ヶ浜町大木囲(だいぎがこい)貝塚、松島町西の浜貝塚など、全国的にも有数な大規模貝塚が集中しています。豊富な海産資源を求め、多数の縄文人が往来した、まさに縄文時代の人口密集地帯とも言える地域でした。

橋本囲貝塚の貝層
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください