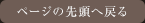ここから本文です。
更新日:2025年3月7日
平成28年度の発掘調査情報
内館館跡第1次調査
多賀城地区大区画ほ場整備事業に伴って発掘調査を行ってきた内館館跡の調査では平安時代の井戸跡を発見しました。
大きく深い穴を掘り込んで、その中に木材を組み合わせた井戸枠を構築しています。

井戸跡調査風景
四隅に丸木の柱を建て、外側に横板を当てて、さらに周囲を土で埋め戻すことによって、土圧で横板を抑え込む構造となっています。
また、それぞれの柱同士は、柱に穿(うが)たれたホゾ穴へはめ込まれた横木で繋がれており、土圧によって柱が内倒れすることを防ぐ造りとなっています。

平安時代の井戸跡
山王遺跡第170~176次調査
山王字山王四区では、隣接する複数の調査区を同時に調査しました。その結果、古代の多賀城南面に広がる道路網のうち、南北大路から数えて西に7本目の道路(西7道路)を確認しました。
その他平安時代の掘立柱建物跡や井戸跡も発見しています。出土遺物としては緑釉(りょくゆう)や灰釉(かいゆう)とよばれる高級な陶器類や、役人の腰飾りである石帯などがあり、この近くで位の高い役人が活動していたことが分かりました。

調査区全体写真
新田遺跡第111次調査
今回の調査は個人住宅新築工事に伴うもので、山王の南寿福寺公園の北西約150mの地点を調査しました。
調査の結果、古墳時代前期の土壙や古代の道路側溝、中世の溝跡などを発見しました。特に古代の道路側溝や中世の溝跡はこの周辺の調査でも発見されており、これらの遺構と同じものであることが確認されました。
また、古墳時代前期の土壙からは土器などがまとまって出土しました。

古墳時代前期の土器出土状況
新田遺跡第115次調査
市内西部の西後地区の調査です。溝跡、柱跡、土壙(どこう)を発見しています。このうち土壙からは、古代の土器がまとまって出土しています。うつわの内側を黒色に処理しているものが土師器(はじき)、赤褐色のものが須恵系土器(すえけいどき)です。これらは、形や製作技術の特徴から、10世紀前葉頃の土器と考えられます。

平安時代の土器出土状況
市川橋遺跡第92・94次調査
城南二丁目における発掘調査で、東西に延びる古代の道路跡(南1道路)を確認しました。道路側溝からは漆紙文書が発見されました。不要になった公文書を漆の蓋紙として再利用したもので、文書には7人の古代の人々の名前が記されていました。現在さらに詳しい分析を進めています。

今回発見された漆紙文書
東田中窪前遺跡第8次調査
東田中窪前遺跡第8次調査は、宅地の造成工事に伴うもので、対象地内は垂直に切り立つ残丘上に位置しています。
調査の結果、古代の竪穴住居跡や溝跡、近世の掘立柱建物跡・井戸跡・溝跡・土壙、多数の柱穴を発見しました。
古代・近世の二時期の遺構が存在し、長い時間生活空間として土地利用されていることが明らかになりました。

調査区全体写真
まとめ
平成28年度多賀城市が行った調査は合計46件にのぼります。したがって、今回紹介した調査は全体のごく一部に過ぎません。個々の発掘調査から得られた成果を繋ぎ合わせ、より広い視点から多賀城市の歴史を解明していく必要があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください