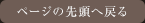ここから本文です。
更新日:2022年4月21日
発掘速報(平成31年2月)
市内遺跡における発掘調査(2月までに実施した調査)
市川橋遺跡(市川字伏石)の発掘調査
1月は図面作成が中心だったことから、新しい遺構の調査に着手していませんでしたが、今月は9・10月にそれぞれ報告した北2道路と西3道路の交差点、掘立柱建物、竪穴住居などの調査を行いました。今回は、珍しい遺物が出土した竪穴住居の調査について報告します。
下の写真は竪穴住居の調査状況を写したもので、住居内の埋土の様子を確認するために、十字に土を残しています。写真上方には、備付けのカマドが設けられています。

カマド付近の様子です。赤く焼けた部分は、カマドの天井が崩落したものです。カマド奥壁中央(写真右側)には、土師器甕が逆さまの状態で置かれています。土器の形を見ると、8世紀代のものと考えられます。

さて、今回発見した珍しい遺物というのは、須恵器の硯(すずり)です。円面硯(えんめんけん)と呼ばれている丸い形をしたもので、脚部4カ所に透かしがあり、縦方向に多くの線刻が施されています。

出土した時は土まみれでしたが、センターに戻ってきて洗浄すると、内側に「占□」のヘラ書きがあることも分かりました。

2月16・17日には東松島市で第45回古代城柵官衙遺跡検討会が開催され、全国の古代史や考古学の研究者が集まり、各地の調査研究成果について検討が行われました。
初日の16日には、多賀城市埋蔵文化財調査センターが行った市川橋遺跡と山王遺跡の発掘調査について報告しました。
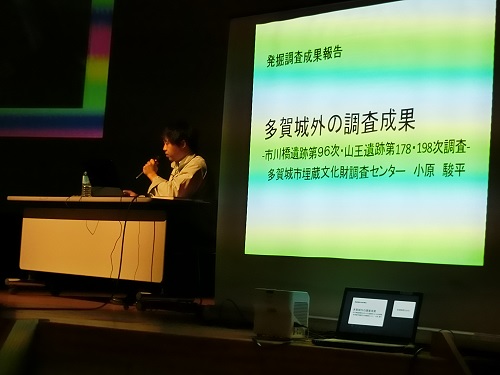
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください